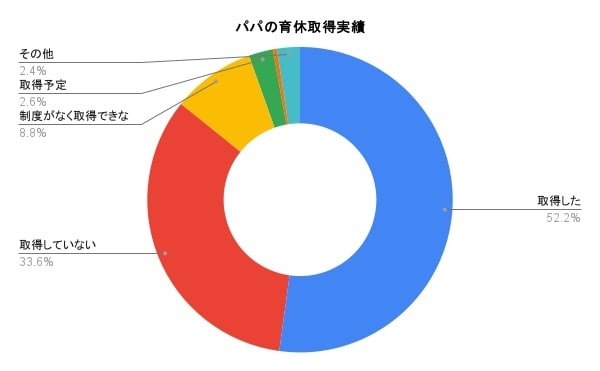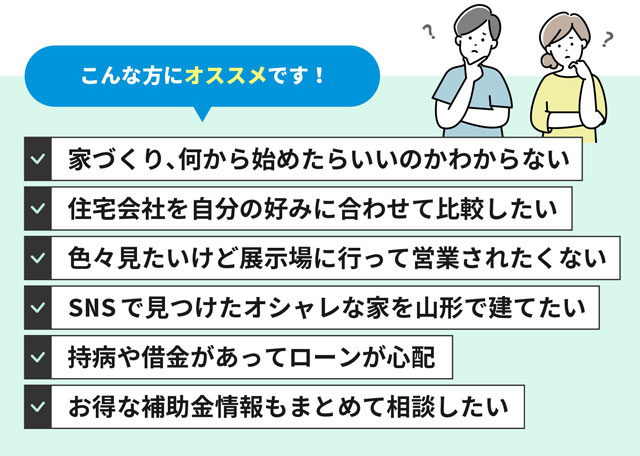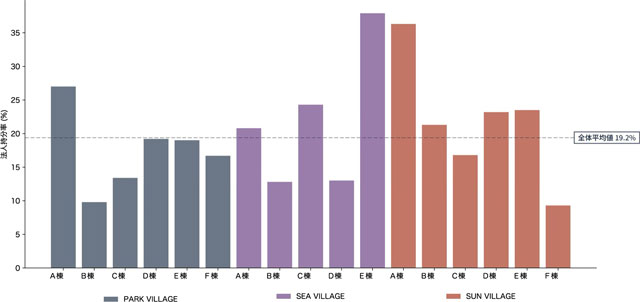ワクチン接種の効果により、来年はコロナ収束の道筋が見え始めるのではないか。そこで事業者としてはコロナ収束後の社会を見据え、〝ポストコロナ社会〟における自社の選択・戦略を今から検討しておく必要がある。
コロナ感染防止や巣ごもり生活から生まれた数々の〝ニューノーマル〟のうち、何が加速し、何が減速するのかを見極めなければならない。中でもコロナ禍で緊急避難的に拡大されたテレワーク、それと軌を一つにする在宅勤務や最寄り駅近くのサテライトオフィスなどで働くライフスタイルのゆくえがこれからのオフィス市場と住宅市場に大きなインパクトをもたらすことになるからだ。
必ずしもリモートワークの拡大だけが理由ではないとしても、このタイミングで電通やリクルートなどが本社ビルを売却し、その後はオフィス面積を減らしてリースバックする動きは大いに注目される。
東京商工リサーチによれば20年度に大規模不動産を売却した企業は東証1部、2部企業だけで76社となり4年ぶりに70社を超えたという。また、三鬼商事によれば、東京都心5区の平均空室率はコロナ感染が始まる前の20年1月の1.53%から今年5月には5.90%まで上昇している。
全社員が毎日出社し、朝から夕方まで一緒に働いていた時代がいずれなつかしく思い出される日が職種を超えてやってくるのだとすれば、今は人間が働く姿の文明史的転換期に当たる。都心への人口流入が減少すれば、オフィス、ホテル、商業施設など都市開発事業全般が歴史的変革を迫られる。当然、住宅事業会社にとっても、用地の選択、住むだけでなく仕事場として必要な要素、スペースをどう取り込むのか、更には二地域居住などの新たなライフスタイルや住文化が本格的に芽生えるかどうかについても真剣に検討すべきである。
オフィスビルはもちろん、住宅も竣工後は何十年も存在し続けるものだけに、コロナ後の社会をどう見通すか、その選択と判断を間違えるわけにはいかない。
今後の25年間で東京圏の生産年齢人口が約400万人も減少するという試算がある。その次の世代となる15歳未満の人口も80年比で45%減少している。
脱炭素やDX化という社会変革も大きな要素だ。更に今後の通信技術の進展によって、オフィスに居なくてもできる仕事の幅はどこまでも拡大し続けるだろう。
また、テレワークや自宅を仕事場にすることについては、単に企業にとっての生産性や従業員管理といった観点からのみ判断するのではなく、働く側の心と健康の問題、家族と触れ合う大切さなど、幸福を求める人間についての深い探求心を持つことも必要になるのではないだろうか。