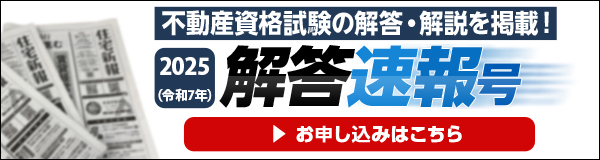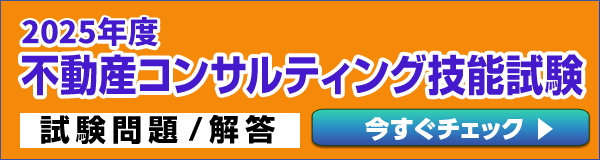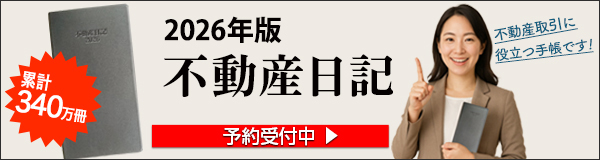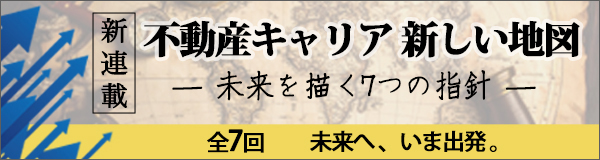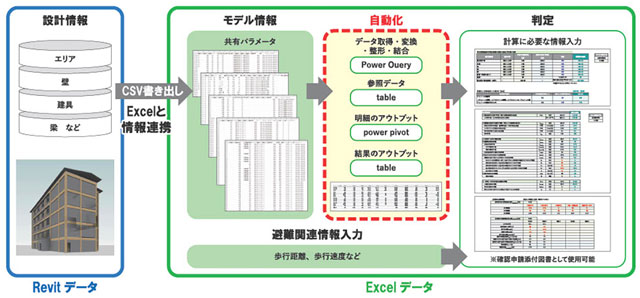社説「住宅新報の提言」 記事一覧
-
社説 重み増す中古市場 コンプラで内需拡大に貢献
国と業界6団体で構成する「宅地建物取引業リスキリング協議会」が9月17日発足した。大手、中堅、中小全ての不動産業従事者全体の資質向上を目指す。DXの推進、空き家問題の深刻化、コンプライアンス重視の傾向など(続く) -
社説 外国人問題で初の女性首相に物申す 市場原理ゆがめる政策に待った
日本国に初の女性首相が誕生。自由民主党総裁の高市早苗氏が21日に招集された臨時国会で第104代内閣総理大臣に選出された。高市首相は緩和的な金融政策と財政拡張を選好していることで知られ、今後の日銀の利上げ(続く) -
社説 宅建試験受付2年連続30万人超 人材流出を警戒し信頼築け
10月19日、25年度宅地建物取引士資格試験が実施される。実施機関の不動産適正取引推進機構によると、今回の申し込み受け付け人数は30万6100人(速報値)で、前年度を1.6%上回り、2年連続で30万人を超えた。宅建士と(続く) -
社説 創造する賃貸住宅管理業 地域連携のポテンシャル示せ
地域連携型の管理の本領発揮が求められている――。国土交通省は9月、賃貸住宅管理業の今後のあり方を検討する議論を開始した。賃貸住宅管理業法の全面施行から丸4年、複雑化する業務と多様化する入居者ニーズを踏ま(続く) -
社説 人材育成の重要戦略 新規事業に多様な効果
大手不動産会社では近年、社内からアイデアを募り、新規事業を発掘しようとする動きが真剣味を増している。もちろんその実現は容易なことではないが、人口減少や単身世帯の増加など社会構造が大きく変化し始めた今(続く) -
社説 16年連続で日本人減少 活路は海外と移民政策
総務省が8月6日に発表した「住民基本台帳に基づく人口」によれば、今年1月1日時点の日本人は1憶2065万3887人だった。前年から約91万人減って09年をピークに16年連続でマイナスが続いている。少子化が及ぼす経済へ(続く) -
社説 外国人の不動産取得に社会的関心 国は基準を、業界はモラルを示せ
7月の参議院議員選挙では、「外国人への対応」が大きな争点の一つとなった。当初は国民負担軽減策等が主流だったものの、実際の選挙戦では、「外国人に厳しい対応をとるか、共生を重視するか」といった姿勢の違い(続く) -
社説 カスハラ対策が義務化 現場再点検で成長止めるな
カスタマー・ハラスメント(カスハラ)対策は、自社の成長戦略を再考する好機となる。行き過ぎた顧客の要求や言動はSNSと匿名性の時代に過熱し、企業経営を揺さぶる。ならば事業主は「働く場、従業員を守る。毅然と(続く) -
社説 介護時代の企業経営 中途採用にも影響
企業経営にとって、従来からの「仕事と子育ての両立支援」に加え、今後は「介護との両立問題」が重いテーマとなってくる。経済産業省によると、家族の介護をしながら仕事をする人(ビジネスケアラー)が2030年には31(続く) -
社説 不動産業界 相次ぐTOB成立 危機対応であれば歓迎
インフレ進行とこれまでの金融緩和により資産価値の増大が続いている。住宅・不動産各社は、大手を中心に今期も最高益をうかがう情勢だ。ただ、過去最高益をたたき出すだけでは今や市場からは評価されない。安定収(続く) -
社説 不動産引取サービスが台頭 リスクの懸念大、適正化で商機に
不動産取引の中でも近年、「引取サービス」が存在感を増している。売買仲介や買い取り(再販)ではなく、民間事業者が有償で不動産を〝引き取る〟サービスだ。構造としては、2023年に開始した「相続土地国庫帰属制度(続く) -
社説 問われる仲介業の真価 自他高める「経営視点」示せ
高額帯取引がけん引した2024年度の売買仲介市場。好調な市況は不動産流通業者の追い風となったが、中長期の成長課題すなわちフィービジネスの源泉は人。顧客獲得の再現性を高めるためには、働き手の獲得・成長、時(続く) -
社説 定借マンションへの期待 ユーザーメリットを明確に
首都圏を中心に近年、定期借地権を活用した分譲マンションの供給が目立ち始めた。不動産経済研究所によると今年は首都圏で2000戸に達する見通しで、ここ数年と比べると約2倍の規模となる。その背景の一つが「地代(続く) -
社説 不動産にクロスボーダー資金流入 活発な取引期待も 危機管理を怠るな
不動産マーケットは、経済の成長と成熟度にリンクする。投資適格物件の市場規模は日本が米国に次ぐ大きさを誇るが、マクロとミクロの2つの側面から日本の投資マーケットにフォローの風が吹いている。人口減少が進(続く) -
社説 中古市場の課題、新築デベにも責任 需給双方が意識の改革を
老朽化マンションが年々、社会課題としての深刻さを増している。高経年物件の増加自体は推測できていたものの、居住者の高齢化や管理不全等が想定以上のリスクとして顕在化していることも一因だ。長期にわたる適正(続く) -
社説 現有戦力こそ成長の動力 評価、キャリアの多様性提示を
業界に新たな仲間が増える。人手不足時代に加わった新たな芽を育て、変化に即した花を咲かせられるか。企業の正念場だ。ただ、企業風土に慣れ、活躍のステップを踏むのは少し先だろう。むしろ、既存社員の成長投資(続く) -
社説 中小業者の人手不足倒産 対策は多様な視点で
人手不足倒産が増えている。帝国データバンクによると、2024年に従業員の退職や採用難、人件費高騰などを原因とする倒産は342件となり、調査を開始した13年以降2年連続で過去最多を更新した。業種別では物流、建設(続く) -
社説 迫られるJリート再編 資本コストを意識した経営を
Jリートが新NISAの対象商品になっていることで不動産証券化協会では個人資金の流入に期待する。個人マネーを取り込もうと投資法人各社も投資口(株式)を分割し、単位当たりの投資額を引き下げて投資のハードルを下(続く) -
社説 持続可能な賃貸住宅経営へ 質的向上が明暗分ける
住宅価格の高騰が、国も強い懸念を示すほどの社会課題となっている。他方、一部の企業・年代を除けば国民所得は低迷が続く。国民の住宅取得能力の低下を受け、賃貸住宅の存在感と重要性、そして質的向上への要請が(続く) -
社説 「住生活基本計画」見直しへ 物申すプレーヤー、議論に巻き込んで
少数与党体制による国会運営が始まった。新年度予算案及び各法案の成立へ向け、各党との濃密な議論が求められることとなる。 住宅・不動産業界にとっても、2025年は今後の住宅政策を考える議論の年だ。国交省(続く)