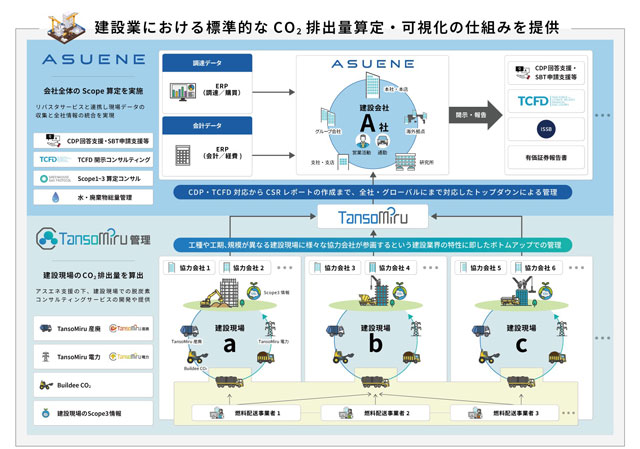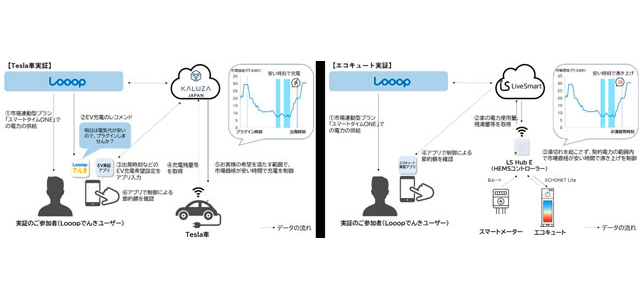賃貸住宅は空き家対策と併せ、社会的な側面からも活用の重要性が増している。その鍵を握るのが、今年5月に成立し、来秋施行される「改正住宅セーフティネット法」だ。改正前の同法では、賃貸住宅の入居を断られる高齢者や外国人といった要配慮者の入居を支えるため「居住支援」が誕生し、それに取り組む協議会や法人の数を増やしてきた。他方、住宅政策と福祉政策の縦割りにより、制度と制度の狭間で必要な支援を受けられない人がいるとの指摘もある中、今回の改正では大家が貸しやすい環境の整備に努める。国交省と厚労省の共管とし、住まいと暮らし、なりわい、ケアをセットにした政策基盤が形成された点が特徴だ。制度の〝すき間〟を埋めるのが居住支援や社会的な活動であり、そのための場づくりを担うのが賃貸管理会社等となる。例えば、改正法の柱の一つとなる「居住サポート住宅」では、エリア内で居住支援や伴走支援に取り組む支援団体や行政、大家などを有機的につなぐ役回りが期待される。
業界内で自発的な動きも出ている。ライフルが11月に開いた「居住支援でつながろう会」は、不動産会社や大家、NPO、居住支援法人などが集い、日々の活動に関する悩みや相談を話し合う場づくりのイベントだ。互いの立場や持ち場を越えて、制度対象や配慮が必要な人への接遇、互いに望ましい連携タイミングなどを語り、共有する一歩を具体化した点は意義深い。同イベントに参加した日本賃貸住宅管理協会は「要配慮者の住宅確保だけでなく、生活全般を支える地域包括ビジネスが賃貸住宅管理業者の新たな商機となる」とし、居住支援に関わる協議会や法人、大家など様々な登場人物をつなぐ役割と包括支援の視点の重要性を強調している。
英国の「ソーシャル・エンタープライズ」など、海外では住宅弱者への支援事業が企業価値を高め、持続的な事業の継続につなげている例もある。そこでは株主等への利益還元ではなく、社会課題解決を通じて利益を上げ、その活動に再投資していくと共に、優秀な人材獲得に必要な報酬や労働環境の整備も追求している。支援対象となる住まい手にとどまらず、働き手や地域価値といった関係者のウェルビーイングを高める仕組みは、人手不足を課題とする日本社会にとっては示唆的だ。
日本でも、LGBTQに配慮した住まい探しなどを行う九州の不動産会社では、従業員のホスピタリティと自社ブランド向上という効用を認めているが、包括視点で寄り添う賃貸モデルの追求は、企業の成長戦略という観点からも有効だろう。地域のストックに深く関わる賃貸管理業者にとっては新たなビジネスモデルを描き、インフラ産業としての地位を確立する好機と捉えるべきだ。少なくとも、その関心を怠ることは商機を逃すリスクとなる。