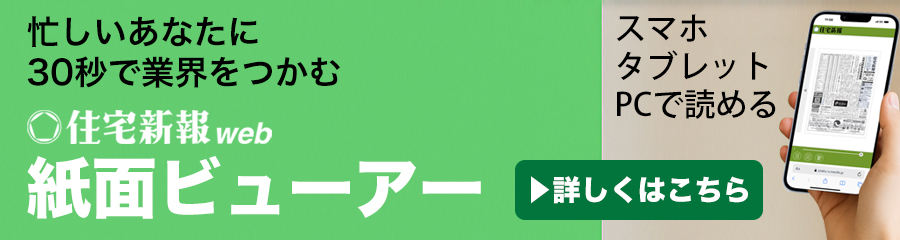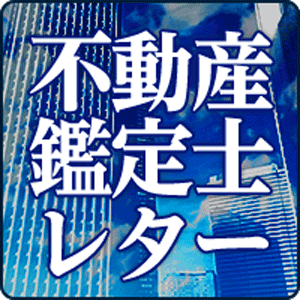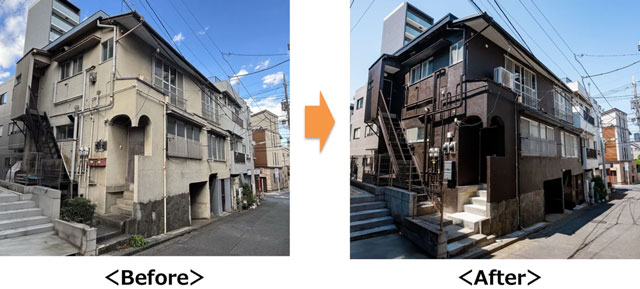「経済現象の7割は〝人口減少〟で説明がつく」とエコノミストの北井義久氏(前・日鉄総研チーフエコノミスト)は言う。GDPの約6割は個人消費だから人口減少が経済に与える影響の大きさからしてもっともな説である。 つまり人口減少が今後少なくとも100年以上に渡って続く(100年後の人口は中位推計で4900万人)とみられている日本の経済は半永久的にマイナス70%の力が働き続けることになる。人口減少(出生率低下)の原因について北井氏は肯定した上で女性の社会参加だというが、筆者は男性の女性化だと見ている。どちらにしてもその潮流は止めようがないので今後の社会(地球)は当面人口減少をむしろ是として考えることが重要になる。ちなみに北井氏によれば世界全体の出生率は1970年以降一貫して下がり続けていて、現在は2.0の水準まで落ちてきている可能性があるという。
適正人口
国土面積が日本の1.4倍のフランスの人口は6837万人、日本と国土面積がほぼ同じドイツの人口は8300万人、イギリスの国土面積は日本の6割程度だが人口は6600万人で日本の5割強である。これらのことから日本の現在の人口(1億2300万人)は多すぎるのではないかと思うのは素人考えだろうか。
適正人口について議論することの難しさは承知しているが、あまりタブー視するのも問題ではないか(これまでにその具体的数字を示した学者は存在しないと言われている)。今こそ国家100年の計に立って議論すべきときだと思う。
そうした中、日本シンクタンク協議会は2月21日、「人口減少時代の日本の舵取り」と題したセミナーを実施した。人口減少が続くこれからの日本の国づくりについて、産業、地域、災害、医療・介護、移民政策などの観点から議論を展開した。
みずほリサーチ&テクノロジーズ、三菱総研、日本総研、三菱UFJリサーチ&コンサルティングというそうそうたるシンクタンクから4名の専門家が参加し、人口減少問題に鋭く切り込む討論会となった。
結論として人口減少問題に効く特効薬はなく、時間が掛かっても地道な施策と地域間の連携、対立する利害をどうコントロールしていくかが重要になるということが分かった。モデレーターを務めた野村総研研究理事の神尾文彦氏は最後にこう締めくくる。「人口減少をうつむきに捉えるのではなく、明るい未来に向けたトランジション(移行のための)デザイン構築へとマインドチェンジするしかない」と。
ここでも適正人口についての議論はなかったが、明るい未来を描くためにも、どの時点でどの程度の人口規模を是とするのかという視点はやはり必要ではないか。
静かな有事
石破茂首相はかつて「人口減少は静かなる有事だ」と言った。パネラーの一人、三菱総研の山口健太郎氏も能登半島地震の災害復興を人口の高齢化と過疎化が阻んでいる問題を取り上げ、こう語った。「地震で受けた災害からの復興ではなく、平時から進んでいた過疎化という地盤沈下からの復興となる。つまり、平時が下り坂で目に見えない災害を受けている」と。
移民受け入れも「静かな有事」となりうる。日本総研の石川智久氏は「産業政策上はIT技術者など高度な人材が必要だが、同時に国内の人材育成も忘れてはならない」と指摘する。24年6月末の在留外国人は359万人で過去最高を更新中。
日本はすでに外国人労働者(現在230万人)なしでは回らない社会になっている。しかし「労働力の受け入れは、人間を受け入れるということ」だと石川氏は言う。エッセンシャル分野も含め産業政策上の観点だけで安易に受け入れを進めれば将来、国のアイデンティティーを失いかねない大きなリスクを抱えることになる。