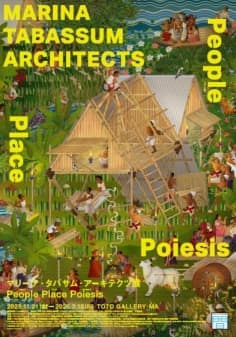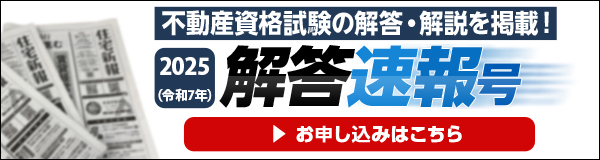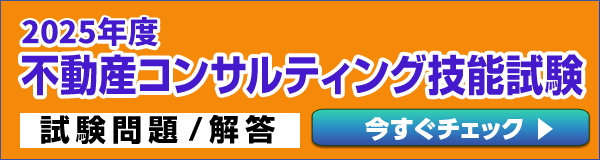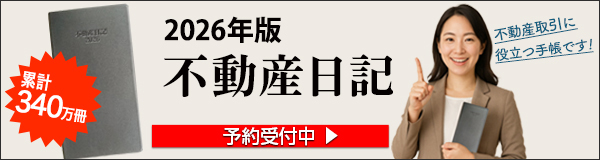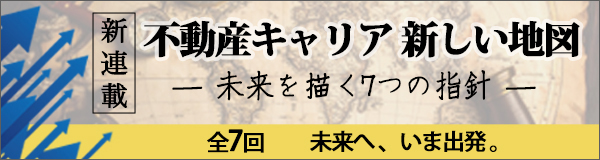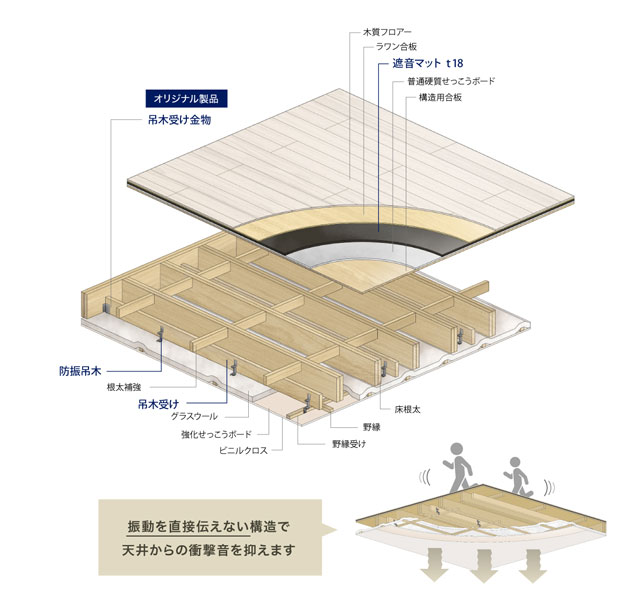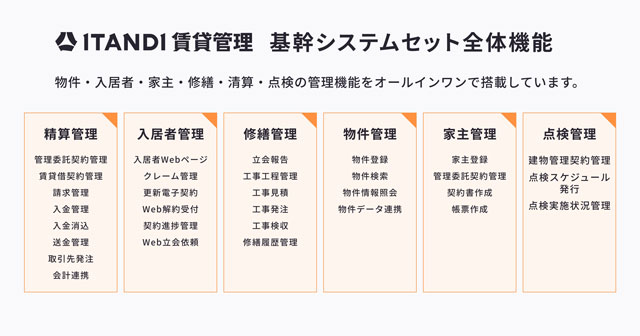住宅を購入する買主から「配偶者も費用負担分相当の持分を持つのですが、それについてどう思いますか」との質問を受けたら、どうアドバイスしたら良いだろうか。
□ ■ □
「不動産の持分は単有が良いと思いますが、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)や売却時の3000万円特別控除(居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除)の利用予定があるならば共有でもメリットがあるのでよろしいかと思います」とのアドバイスが妥当だと思う。 共有は、財産を持つ安心感を得る以外メリットはほぼない。ただし、共有者も税控除を利用するようならメリットがあるので別だという意味だ。そうでなければ、相続で話がまとまらないなどやむを得ない場合を除き、「共有は避けた方が良いですね」そのようなアドバイスが基本となるだろう。
単有は単独所有のことで登記名義人が1人のこと。一方で、共有は登記名義人が複数人いて共同所有している状況を指す。不動産の売却や建て替え、リフォーム、ローンの借り換え、その他何かと利用をする場合は登記名義人の承諾が必要となる。単有で1人なら「やる/やらない」の意思決定は早いが、共有で複数人いると承諾を得る人数が多い分意思決定は遅くなる。
また、手続きも人数分の手間暇や時間がかかる。スムーズに手続きが進まない。更に共有の場合、1番問題となるのが共有者内で「やる/やらない」で意見が割れた場合だ。そのままだと売却やローンの借り換えなど何もできないことになる。このことだけでも共有はデメリットが大きく、避けた方が良いとも言えなくはない。
「売却して住宅ローンを返して出ていきたいが、持分を持っている配偶者が住み続けたいので売却はしないと言っている。どうしたら良いか」
筆者は離婚によるマンション売却の相談を受けたが、共有者が承諾しない限りは売れない。有効な解決方法は提示できずうやむやになった。共有の弊害と言える事例だ。
一方で共有者も住宅ローンを組んで購入する場合は、持分を持つ(金融機関から共有を指示されるが)と住宅ローン控除を買主とともに共有者も利用できるので、より税控除を多く利用できてメリットが大きい。中古住宅なら最大140万円の所得税等控除(適用要件あり)の2人分、世帯で280万円の税控除を受けられることになる。
同様に自宅を売却の際に高値で売却し6000万円の利益が出た場合、単有なら3000万円を差し引き残り3000万円に長期短期の譲渡所得税としても課税だが、共有なら更に3000万円控除をして利益0円として課税なしとすることもある。メリットはあるので検討の余地があると言えよう。
【プロフィール】
はたなか・おさむ=不動産コンサルタント/武蔵野不動産相談室(株)代表取締役。
2008年より相続や債務に絡んだ不動産コンサルタントとして活動している。全宅連のキャリアパーソン講座、神奈川宅建ビジネススクール、宅建登録実務講習の講師などを務めた。著書には約8万部のロングセラーとなった『不動産の基本を学ぶ』(かんき出版)、『家を売る人買う人の手続きが分かる本』(同)、『不動産業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書』(技術評論社)など7冊。テキストは『全宅連キャリアパーソン講座テキスト』(建築資料研究社)など。