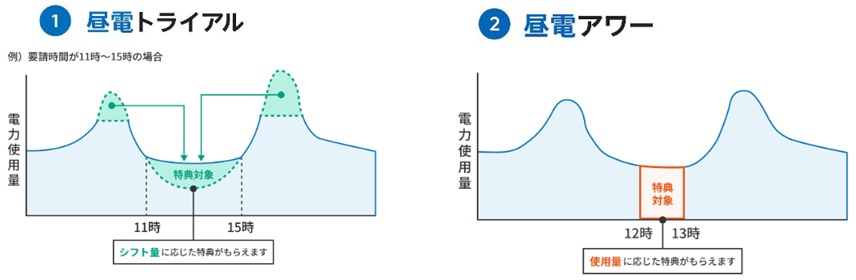在日アメリカ大使館は4月3日、ホームページ上で日本の新型コロナ検査不足を指摘し、〝有病率〟を正確に把握することが困難として在日アメリカ人の早期帰国を促した。
アメリカやヨーロッパに比べ日本の感染者数が少ないのは「幅広く検査をしないという日本政府の決定」(同ホームページ)によるものとしているが、それが事実なら日本の新型コロナウイルスの感染が今後どこまで拡大するのか予断を許さない。しかも、専門家の間でも「かろうじて持ちこたえている」という意見と、「既に手遅れ」という意見が鋭く対立している状況だ。
新たな文明へ
開き直るわけではないが、一般国民としては一刻も早い収束を願うことと、その後の社会について考えることぐらいしかできない。
ややオーバーかもしれないが、世界が今回のコロナとの目に見えない戦争に勝利することができれば、人類はまったく異なる文明に向かって進み始める予感がなくもない。その場合、住宅・不動産業界にはどんな変革が訪れるのだろうか。
まず、あらゆる職種において考えられるのが自宅で仕事をする「在宅勤務の日常化」である。大企業の多くが今回は感染防止のために緊急避難的に導入したが、その壮大な実証実験はまずまずの成果を上げつつあるようだ。企業がそのせっかくの成果をコロナが収束したからといって無に帰すとは思えない。
都心に広大なオフィスを構えなくても、今後も発達し続ける情報通信技術を活用すれば、更に多くの仕事をこなせることが証明されたわけである。都心に大規模なオフィスを供給し続けてきた不動産業界にとっては、コペルニクス的転回とも言える事態である。
何十年先になるのか、それとも存外早くやってくるかは分からないが、莫大な時間ロスを生む〝通勤〟という不合理なスタイルが、この世からなくなる日はいずれやってくるだろう。多くの職種はテレワークが基本となり、仕事先に出向くのは特殊な研究機関に勤務している人たちなどに限られるようになるのではないか。
消える〝通勤〟
そうなれば、住まいのあり方も変わる。住まいに仕事場としての機能が加わることになり、テレワークのための環境整備はもちろん、夫婦それぞれの仕事場(書斎)が必須となる。なにしろ、その頃は夫婦共働きが勤労者世帯の9割以上(現在は約7割)を占めているだろう。
夫婦それぞれの書斎が必要になるとすれば、ちょうどこれまでの子供部屋2つ分となる。子供部屋の確保が優先されたこれまでの「子育て中心」的住まいづくりからは一変し、まずは一家の働き手のためのスペースが最優先されるようになる。
もちろん、子供部屋がつくられなくなるということではない。ただ、住まいづくりには資金的制限が伴うわけだから、何を優先するかの問題である。生活の糧を得るための仕事場が最優先されることは当然だろう。
現代の盲点
住まいに、神聖な親の仕事場としての機能が加わるということは、子が真剣に働く親の姿を間近に見ることになり、親子の距離を縮める契機になる可能性がある。というよりも、子供が家庭という場を通して社会の風に触れることになれば、社会のあり様と厳しさを子供ながらに感じ取ることができるようになるのではないか。
現代の盲点は、社会の最小単位である家庭が社会と切り離され、社会から家庭を見ようとしても、家庭から社会を見ようとしても互いにブラックボックス化していることである。親子間の断絶も、少子化も、離婚増加も、単身世帯(特に高齢者)の増加も、すべてはそこに病巣がある。
在宅勤務という新たな文明が社会と家庭との溝に光を通すことができれば、日本社会を再建する力になりうるのではないか。とすれば、新しい家族関係構築の場となるこれからの住まいのあり方が日本の未来を担っていると言っても過言ではない。
(住宅新報顧問)















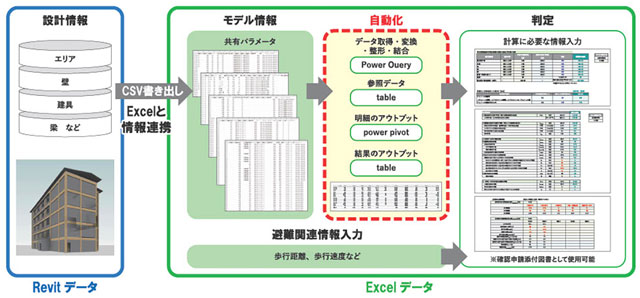



.jpg)