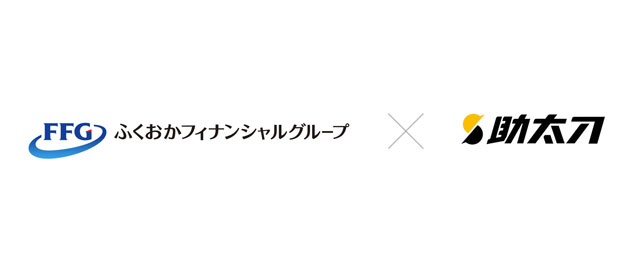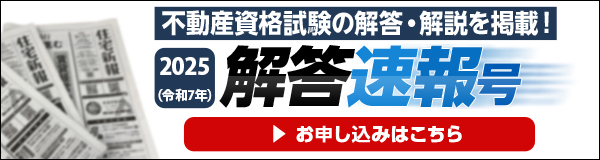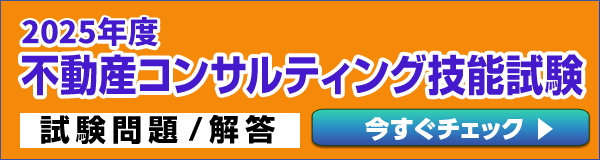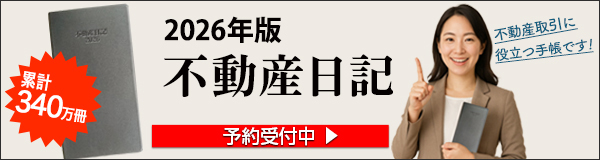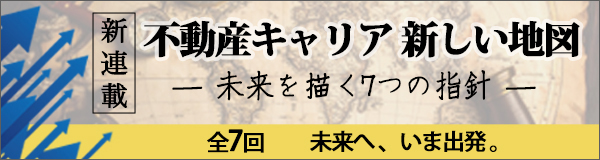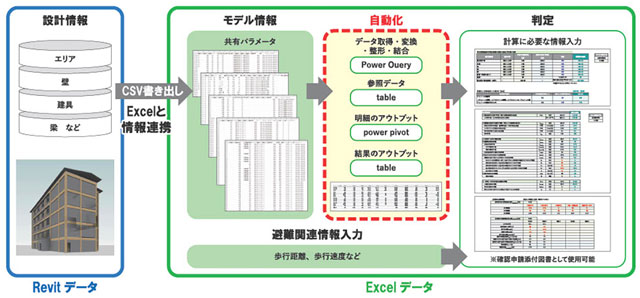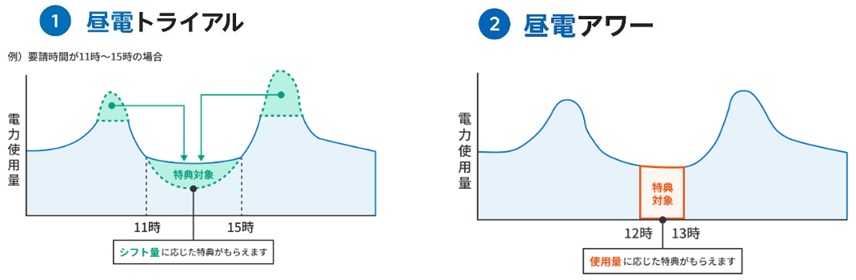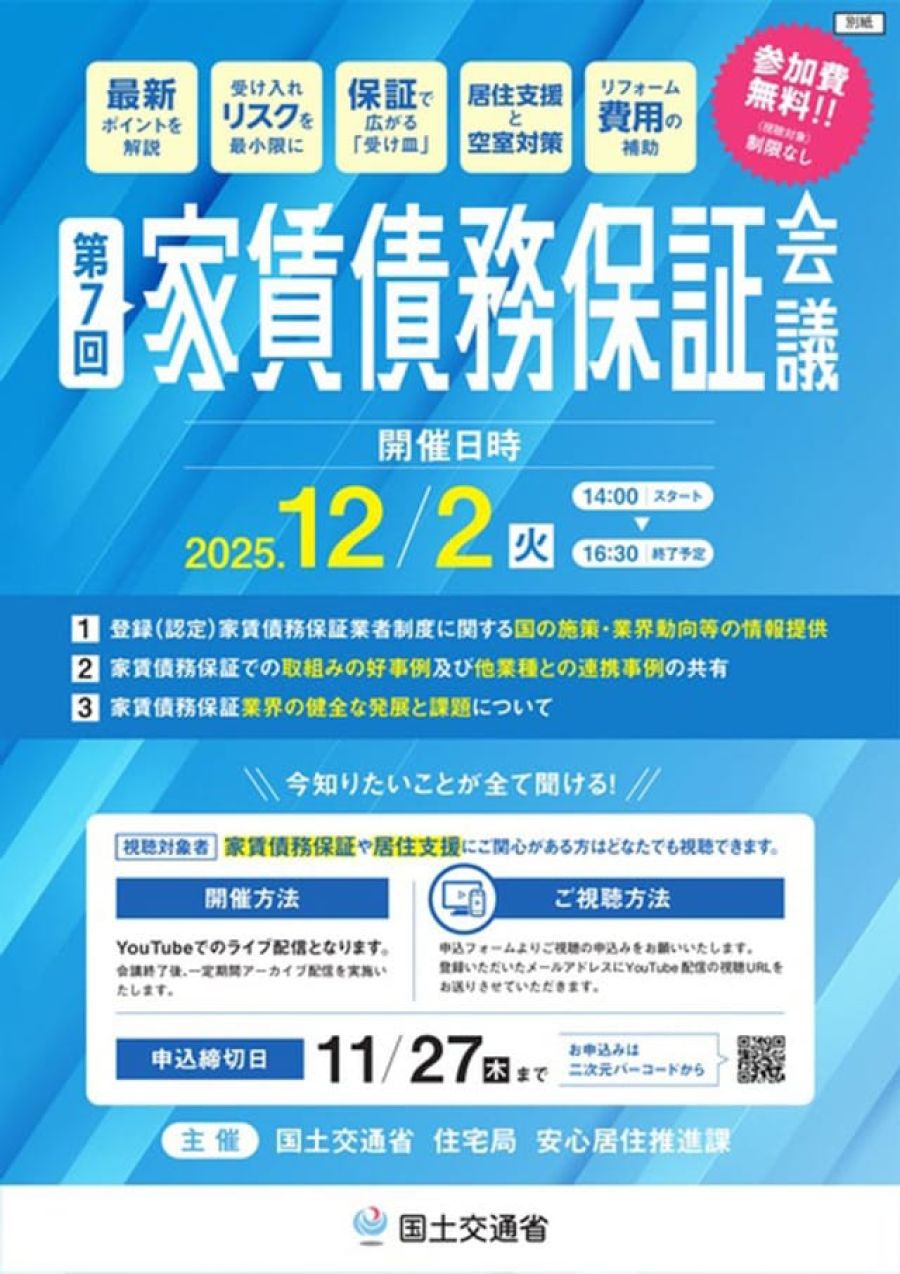仲介手数料とは言うが「コンサル手数料」とは言わない。なぜか。それはともかく、コンサル業界では今でも依頼者に対し〝報酬〟を請求しにくいことが大きな課題となっている。仲介手数料も本来なら「媒介報酬」と言うべきところだが、「仲介手数料」と表現することで、報酬規程の上限金額が受け取りやすくなっている。手数料という言葉には「あらかじめ定まった金額」という意味合いがあるし、当然払うべきものという感覚もあるからだ。しかし、だからと言ってコンサル業界が「コンサル手数料」という言葉を使うことは永遠にないだろう。
◇ ◇
「報酬」と「手数料」は本質的に異なる。いずれも一定の役務やサービスに対する対価だが、報酬はそこに感謝(謝礼)の思いがあるのに対して手数料は単に決められた料金を払うだけである。だから、住宅ローンの借り換え手数料や賃貸住宅の更新手数料を感謝しながら払う人はいないだろう。
では、〝手数料〟を受け取っている媒介業務は単に一定の手続きをしているだけなのだろうか。そんなことはありえない。例えば買い手のためには希望条件に合った物件を探し、あらゆるリスクをチェックし、周辺環境を調べ、売主との価格交渉を行い、住宅ローンの説明・あっせん(無償)も行う。この世にまったく同じ不動産は存在しないのだから、提供される労力も気遣いも同じものにはなり得ない。しかも最終的に成約に至るかどうかさえ不明だ。これほど、専門的で依頼者の利益保護まで義務付けられている高度な仕事に対する対価を手数料と呼ぶのはいかにもおかしい。これは考えようによっては媒介報酬規程(上限)が法律(大臣告示)によって定まっているゆえにいつとも知れず根付いてしまった慣習と言えなくもない。
ちなみに。弁護士も税理士も司法書士も当初はそれぞれの報酬が協会規定で縛られていたが、弁護士報酬は04年度から、税理士報酬は02年度から、司法書士報酬は03年から自由化された。要は仕事に臨む姿勢の問題で、法律や協会によって規制されていては真に依頼者の利益を守り、その要望に応えることができないからである。
本質は同じ
媒介(仲介)もコンサルも依頼者からの求めにいかに真摯に応えるかが問われている。だとすれば、報酬の額を最初から決めておくことはそうした理念と矛盾する。最初からもらえる報酬額が決まっていればおのずとサービスの量も質もその範囲内にとどまるからである。それでは真に依頼者の利益追求を成し遂げたとは言い難い。もちろん、その範囲で納まることもあるだろうが、さらなる作業を加えなければならなくなることもある。
コンサルティングの場合、プロジェクトの進行具合に応じて必要になるコスト(依頼者にとっては報酬額)をその都度提示しながら進めていく手法が取られているのはそのためである。あくまでも依頼者の〝最適解〟を追求することが目的だからである。
媒介の場合はコンサルティングほど長い期間、もしくは多くの段階を要することはないだろうから、当初におよその金額(相場)を提示し、あとは依頼者の要望に添えた度合いに応じて多少のプラスが(場合によってはマイナスも)あることの承諾を得ておけばいいのではないか。
◎ ◎ ◎
他の士業も自由化後は各事務所が自由に報酬を設定できるようになったが、おのずと従来からの相場の範囲であり、その額については事前に依頼者に説明する(もしくは表示する)ことで混乱は起きていない。
不動産業界にあっても、21年に全面施行された賃貸住宅管理業法は管理報酬に規制を設けていないし、国交省がコンサル報酬に規制を設ける動きもない。媒介報酬だけがいまだ自由化されていないのには疑問を感じざるをえない。