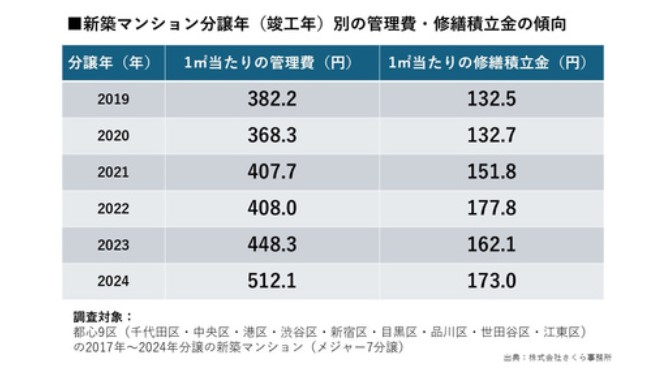日本は今、単身世帯が全世帯の38%を占め、30年には2025万世帯となり4割を超える。うち85歳以上の単身者(一人暮らし世帯)は225万人で20年比54%も増加する(国立社会保障・人口問題研究所=社人研・24年推計)。まさに自宅が現代版〝姥捨て山〟になろうとしている。深刻な高齢者の独居問題を直視し、その元凶ともいえる核家族社会の持続可能性を考える。
◇ ◇
〝人生100年時代〟という言葉には長寿大国への期待も込められているが、その裏では単身世帯の高齢化が急ピッチで進んでいる。社人研によれば85歳以上の単身者数は20年146万人、30年225万人、40年289万人と20年間で2倍近くに増加する。
一般に高齢者といわれる65歳以上に枠を広げればその単身生活者の数は20年の737万人から30年には887万人、40年には1041万人と増加する。子供が独立すれば親元から離れ、新しい世帯を形成する核家族社会の宿命である。
子育てを終えた夫婦はいずれ配偶者を失い一人暮らしになる。それでも日本の高齢者の多くは「子供の世話にはならない」ことを美徳としている。しかし、世話になるもならないも〝順繰り〟が当然のこの人間社会で、そうした自己犠牲的な考え方・生き方が本当にあるべき人間社会の姿なのだろうか。それが社会の底辺を支えるべき家族という組織のあり方として本当に〝善〟だろうか。
SDGsは持続可能な開発目標として17項目を掲げているが、そのなかのひとつに「住み続けられるまちづくり」がある。住み続けられるまちには住民同士の豊かなコミュニティがあり、その地域社会を支える最小単位としての家族の絆がなければならない。
しかし、一世代ごとに〝細胞分裂〟を繰り返すごとき核家族に地域社会を支える強固な力があるのだろうか。
核家族は親子という最も濃密で強い血縁関係が支配しているため、より緩やかで幅広な親族関係や地縁に基づく人間関係が入り込む余地が少ない。そのため、核家族家庭は外に対する開放性に乏しく、どちらかといえば閉ざされた居住環境になりやすい。
例外的に団地などの集合住宅では同じ低学年の子供を持つ母親同士が交流を深めることはあるが、それも長くは続かない。子供の成長につれ、進学先の違いや転居などでそれぞれの生活事情が違ってくるからだ。
本質的に閉鎖的性格をもつ核家族家庭は、地縁に基づく日本の伝統的地域コミュニティを衰退させ、地域社会を疲弊(ひへい)させる方向に作用する。では、そのような弊害をもつ核家族社会から日本はどのように脱却していけばいいのだろうか。
筆者はその第一歩が増え続ける空き家を活用し、親世帯と子世帯が近居できる環境を整備していくことだと考える。近居といえば、近年は大手ディベロッパーが大型の住宅団地を開発する際にその一角にサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)などを整備し年老いた親と子世帯が近居できるようにした事例があるが、筆者の構想は少し違う。
社会工学的変革
最も大事なことは、親世帯が独り住まいや要介護状態になってからの近居ではなく、子供が独立して新たな世帯を持つときから親世帯の近くに住むようにするというものである。結婚した子供が親の家に同居する二世帯居住は面積的に無理があり、精神的にも難しいが、親の家の近くにある空き家を取得、または賃借して住むのであれば難しくないのではないか。
これからの日本の街づくりにおいて、より重要なのは新たな住宅地の開発ではなく既存住宅地の再活性化である。親子2世代、または3世代の近居推進を国家的政策とし、地方自治体による経済援助と民間企業の熱い思いを巻き込んだ社会工学的変革として推進していくべきである。
(次号につづく)










.jpg)