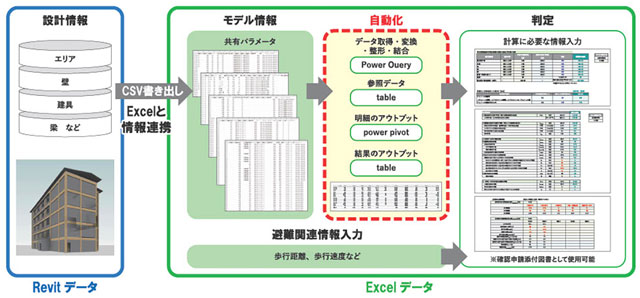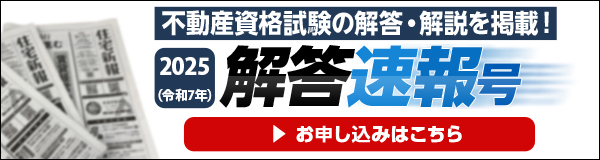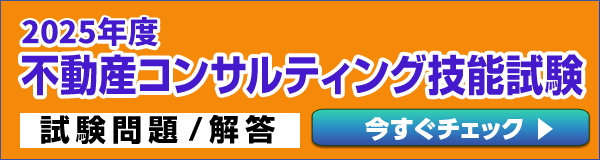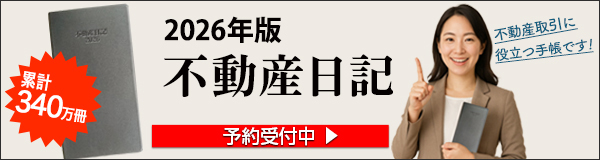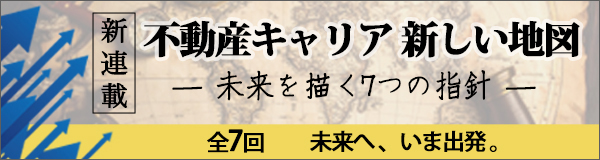「道路の建築基準法の扱いを教えてください。また、建築計画概要書、台帳記載事項証明書をいただけますか」
法令上の制限の調査も3回目だが、今回は対象不動産周りの建築基準法について、窓口は建築指導課で調べていくことになる。具体的に調査する事項は大きく4点。
1点目は対象不動産に接する道路の建築基準法の扱い、2点目は建築の制限や緩和、3点目は対象不動産に建物がある場合は建築確認番号や検査済番号、4点目は特定建築物の場合は定期報告の提出。おおまかにはこの4点だろう。その他にも買主の購入目的に関係することや、皆さんの調査事項があるなら合わせて窓口で確認をしていく。
まず1点目。対象不動産に接する道路の建築基準法の扱いを窓口で確認する。建築基準法では土地に建築ができる条件として「建築基準法の幅員4メートル以上の道路に敷地が2メートル以上接していること」とある。新たに建築物ができるか、再建築が可能かを知るために、接する道路が「建築基準法の道路」なのかを調べていく。「建築基準法の道路」とは、主に建築基準法42条の道路の定義で書かれている道路のことだ。よく公道=建築基準法の道路と勘違いしやすいが、公道や私道は権利や管理の話なので建築基準法の話と別となる。42条1項1号道路や42条2項道路など建築基準法の道路ならOKだが、中には建築基準法に該当しない道路もあることに注意しよう。
2点目は日影規制や角地緩和など建築物の高さ、建蔽率、容積率の制限緩和について窓口で確認しよう。
3点目は建築確認番号と検査済番号を確認する。併せてこれら番号が記載されている建築計画概要書、台帳記載事項証明書も取得しておこう。建築計画や完成時の段階で建築基準法に適合した建築物であるかを確認するために必須だ。確認番号や検査済番号がなければほぼ違法建築だが、番号があっても実際の建築と異なる面積や内容なら違法性を疑った方が良いだろう。
4点目は特定建築物の場合。特定建築物とは不特定多数が出入りして規模が一定以上のもの。その場合、建築物や設備の状況を定期的にチェックし、定期報告(書)をしなければならないが、それが出されているのかを確認する。出されていなければ法令違反の状態になるので注意したい。
なお、特定行政庁でない市区町村役場には建築指導課がないので注意したい。特定行政庁とは建築主事がいる役場のことで、建築主事は建築基準法を取り扱える資格をもった公務員のことだ。事前にホームページを見ておけば市区町村役場が特定行政庁かどうか、特定行政庁でないならどこに行けば良いのか(都道府県かその出先機関)記載している。出先機関は遠方にある場合も多いので、調査には時間の余裕を持って臨みたい。
□ ■ □
【プロフィール】
はたなか・おさむ=不動産コンサルタント/武蔵野不動産相談室(株)代表取締役。
2008年より相続や債務に絡んだ不動産コンサルタントとして活動している。全宅連のキャリアパーソン講座、神奈川宅建ビジネススクール、宅建登録実務講習の講師などを務めた。著書には約8万部のロングセラーとなった『不動産の基本を学ぶ』(かんき出版)、『家を売る人買う人の手続きが分かる本』(同)、『不動産業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書』(技術評論社)など7冊。テキストは『全宅連キャリアパーソン講座テキスト』(建築資料研究社)など。