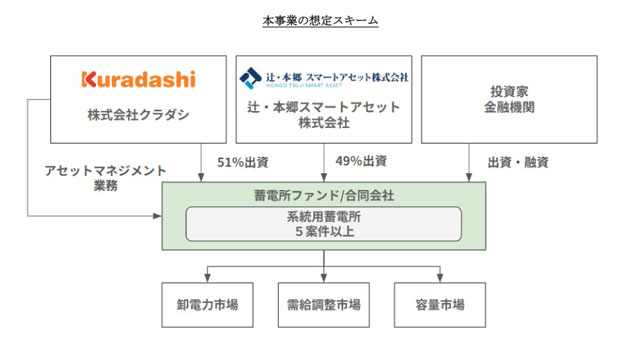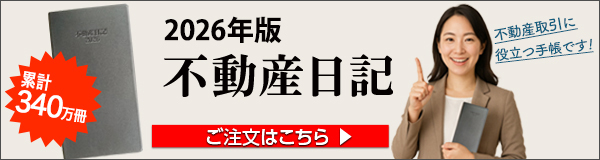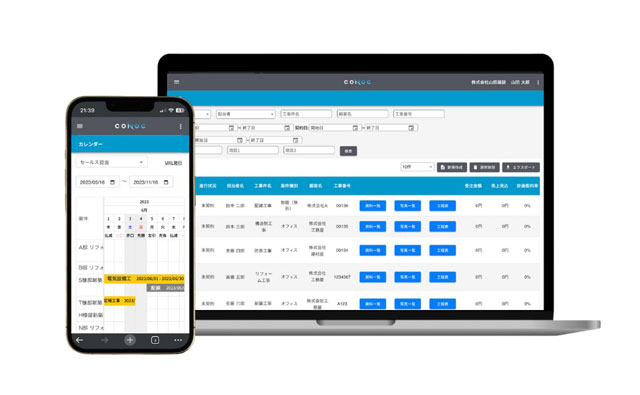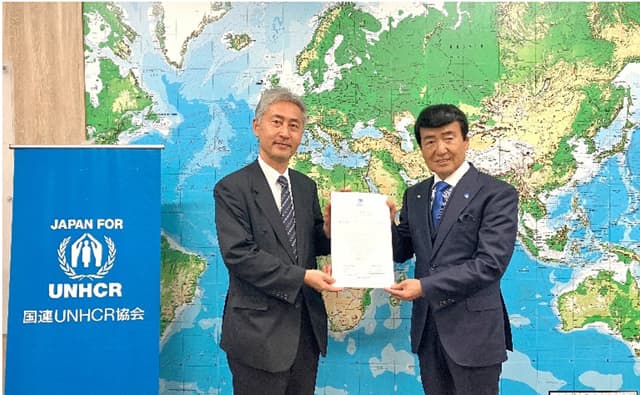改正住宅セーフティネット法の施行から5年。住宅と福祉が連携して進める住宅セーフティネット(SN)制度は好調に参画団体を増やす一方、質的拡充が問われる局面を迎えている。特に高齢者の居住支援は、その市場規模や複合的な課題解決の必要性から住宅確保要配慮者(要配慮者)に対する居住支援の試金石となる。今こそ賃貸住宅オーナーの制度理解を促し、居住支援に参画する事業者などのメリットを明確に発信するときだ。
21年9月の総務省の発表によると、日本の総人口に占める65歳以上の割合は29.1%で過去最高を更新した。更に約20年後の40年には3人に1人が高齢者になると見込まれ、賃貸住宅で暮らす単身高齢者の増加が予測される。
国土交通省が全国の賃貸住宅事業者に対し、要配慮者に対する入居制限の状況と必要な居住支援策を調査(令和元年度)したところ、入居制限されているのは高齢単身世帯が44%、高齢者のみの世帯が38%となった。これは低額所得世帯(49%)や外国人世帯(58%)よりは低いものの、ひとり親世帯(15%)や子育て世帯(10%)よりは高い水準だ。高齢者に対する入居制限の大きな理由には、「孤独死などの不安」「保証人がいない」が挙げられており、同調査でもこれらに必要な居住支援策として「見守りや生活支援」「死亡時の残存家財処理」などが指摘されている。
全日本不動産協会(全日)は、地方本部や消費者に対する情報発信と共に、「公益法人として入居差別解消に努め、適正な不動産取引を推進する」と位置付ける。SN制度の展望については「大家の制度理解の促進と、それを担保するサービスや支援の拡充が必要」と指摘。全日グループの全日ラビー少額短期保険では21年5月、入居者に相続人がいない場合、大家が清掃費用等を直接請求できるよう賃貸住宅での孤独死対応を強化した。同6月からの半年間で9件の宅内死亡案件が発生。うち4件の請求者が建物所有者で、早速対応の成果が出始めている。
多様な居住ニーズに対応 居住支援協議会 持続に予算、実施者、人材育成
不動産業者も参画する居住支援協議会の取り組みを見てみよう。全国の設立状況は111協議会。「30年度までに日本の人口カバー率50%」とする国の目標の中間地点を突破したが、その取り組みは地域の事情や要配慮者の課題によって様々だ。
16年6月に設立された川崎市居住支援協議会には不動産団体5団体、居住支援団体として高齢者住宅財団や社会福祉協議会など13団体が参画。庁内部局は高齢者・障害者・外国人等の施策を所管する13課室で構成され、市の住宅部局と川崎市住宅供給公社が共同事務局として主導する。
「入居を拒まない物件を増やす取り組み」「効率的な物件探しの相談・支援体制の構築」の2つを実施。主な成果として、同協議会の「すまいの相談窓口」で行う、高齢者等と不動産店・支援団体とのマッチングを挙げる。具体的には要配慮者からの住み替え相談への対応について、同窓口がハブとなり、複数の協力店(不動産店)へ物件情報の提供を依頼。実際に物件情報の提供があった不動産店の窓口で、要配慮者に契約手続きを行ってもらう仕組みだ。
同窓口は1カ所だが、相談には電話でも対応。川崎市住宅整備推進課によると、現在約8割が電話による相談。毎月約40件の相談の内訳は、高齢者が約40%、障害者が約20%、外国人・子育て世帯が計約10%だ。主な相談内容は住まい探し関連で、「立ち退きによる退去と新居探しといった複合的な問題を抱える相談者も増加。住まい探しに加え、入居後の生活支援が必要な人には支援先につなげている」(同課)。高齢者の場合、「バリアフリー住宅が少ないため、車いす利用者への住まい探しに時間がかかる」「保証会社の利用ができず、住み替え先が見つからない」など支援が難しいケースもあるという。
要配慮者は、情報弱者である場合もあり、コロナ下では情報周知・啓発の方法が課題。同課では「まず福祉的な支援者へ居住支援についての周知を進め、支援者と連携することが重要」とし、コロナ禍によって難しくなった不動産店や区役所窓口への手続き同行支援の代替策が必要と考える。不動産事業者に対しては、入居中の要配慮者に変化があった場合、支援者や市へ連絡するなど協力を期待している。
制度検証に意欲
高齢者の賃貸住宅入居に対する理解促進に注力するのが全国宅地建物取引業協会連合会(全宅連)だ。全宅連不動産総合研究所では要配慮者の居住確保に関する現状や高齢者の入居に必要な支援策など、3年間の調査研究成果を21年3月に公表。「国交省が公表した『人の死の告知のガイドライン』の検討、制定につながっていった」と振り返る。更に22年度は研究テーマとして「コロナ禍の住宅困窮者」を構想中とし、予備調査としてSN制度の実態や課題等の把握に取り組むという。全宅連は「研究所の調査を生かした取り組みにつなげる」とし、不動産事業者がSN制度に持続的に参画するための方法を検証する考えだ。
具体的な居住支援を提供していくためには、より地域に密着した視点が不可欠となる。国の調査でも、協議会の活動として都道府県ではSN住宅や制度・相談窓口などの「情報提供」、市区町村では関係事業者への働き掛けを含む「居住支援」が多い傾向を示しており、それぞれの役割を整理し、連続的につないでいく視点が鍵を握る。情報提供のあり方も含め、要配慮者の需要が高い地域で案内できる登録物件は十分か。公的機関による民間賃貸の借り上げなど、自治体が担う役割の検討を指摘する声もある。
国土交通省住宅局安心居住推進課課長補佐の田代洋介氏もまた、「大家、自治体、要配慮者など、様々なプレーヤーが交わる中で、情報提供、周知浸透の強化は課題」と受け止める。川崎市住宅整備推進課は協議会の役割について「住宅と福祉が連携して協議する場であること」と説明。5~10年後を見据え、「既存の制度や居住継続に必要な支援の活用に加え、居住支援協議会を継続して運営し、必要な支援を実施していくための予算や、居住支援法人などの実施主体を増やすこと、居住支援のハブである相談窓口の相談員等の人材を育成することが必要」(同課)と指摘する。
国交省の田代氏は今後の波及拡大に向けて「経済的支援に関する要件緩和も含め、オーナーの拒否感を和らげ、入居制限を減らしていく。安定的な住まいの提供へ、関係団体と連携を強化したい」と語った。